(第1回)池上彰のカバンは重い
1994年の4月から「週刊こどもニュース」を立ち上げようという1993年11月、
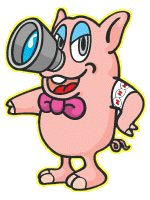 こども番組担当のディレクターだった33歳の杉江義浩はNHKのある一室で池上彰と初めて出会った。
こども番組担当のディレクターだった33歳の杉江義浩はNHKのある一室で池上彰と初めて出会った。
僕は池上のカバンを持ってみた。ずっしりとした感触。開けてみていい?と聞くと、どうぞというので開けてみた。ハードカバーの新刊書が5冊入っていた。へえ、こんな難しい本読むんですね、という杉江に池上は「君たちは読まないの?」と不思議そうな顔をしていた。
僕が驚いたのはそのことではない。翌日も、その翌々日もまったく別の新刊書がカバンの中に入っていた。毎日5冊以上の本を読むのは、池上彰にとってごく日常的なことだったのだ。池上は毎日出局すると2時間かけて新聞5紙を隅から隅まで読みつくす。これもまた池上彰にとっては日常的な習慣であった。それまでアニメや人形劇を演出してきた番組制作局こども番組部のディレクターたちには、そんな習慣はなかった。ただただ池上さんを尊敬のまなざしで見つめるばかりであった。
しかしまだ、この時の池上彰は「知の達人」ではあったが「伝える達人」ではなかった。このことについては書籍、“これが「週刊こどもニュース」だ” (集英社文庫)にも書かれている。
この時池上彰43歳、NHK報道局科学文化部の記者であった。社会部に所属して記者として豊富な取材経験を持ち、首都圏ネットワークのキャスターとして出演経験もあったが、あくまでもあまたいるNHKの優秀な記者の一人である、という以上の何者でもなかった。
そんな池上が週刊こどもニュースという番組と出会う。この番組の立ち上げ、そして主に最初の3年間、試行錯誤を続けながら池上彰は育っていくのである。出会いはビッグバン、毎週の生放送は修行の場であった。総理大臣の名前を聞いてもさっぱり答えられない、無知で無垢な3人のこどもたちと真っ向から向かい合いながら、池上は自問自答した。自分がいくら知識を持っていても、それを伝えられなかったら意味がないのではないか。相手のレベルが低すぎるということを理由に、解説から逃げてもいいのか。ニュースの専門家が専門家同士で分かり合えているからと言って、庶民を置いてけぼりにしたまま報道していいのか。これらの問題に池上彰は「週刊こどもニュース」という番組の放送を続けながら、自分なりに答えを見つけていく。
池上彰はいかにして今のような池上彰になったのか。それは「週刊こどもニュース」時代の池上の姿をつぶさに見ていくことで、次第に明らかになっていくのである。
(つづく)

